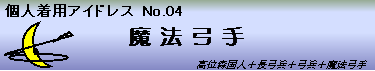魔法弓手の誕生
Unprecedented magic bow
1.承前
「最終目標は『弓矢で爆撃機を落とす』あるいは『弓矢で駆逐艦を撃破』です!」
「それは何処の某塾長だ」
「えーどっかのヤクザの元組長なじーさんじゃなくて?」
「……共通項はハゲでジジイということでよろしいか」
「歳の話はするなーーーー!」
〜開発チーム、初回会議によるトンデモ発言記録。この頃はまだ冗談だった。
この恐るべき武装の開発、そのきっかけは、まだ長弓の改良を行っていた時期に遡る。
元々、るしにゃん王国弓兵部隊の装備には戦闘補助の為の魔術が施されていた。これは、様々な問題――森国人の種族的特徴として乏しい筋力を補う為、或いは飛距離や安定性を高める為のものである。
これらの術は魔術構造ひとつひとつを取ってみればごく簡単な――それこそ基礎課程で学ぶ単純な構造レベルのものであり、効果それ自体もそれほど強力なものではなかった。
にも関わらずこの構造が採用されていた最大の理由は、使用されている魔術そのものにあった。
高位魔術は例外なく複雑な構成を伴うものである。これらは非常に繊細であり、施した後も台座(この場合は弓や矢の本体)についた些細な傷で暴発する例が少なくない。また、他の魔術によるわずかな干渉でも、重大な事故を招くことが経験として知られていた。
身を守る為の武器で、自分や守るべき存在である仲間を傷つける事はあってはならない。
この為、弓そのものの開発の最終段階では魔術的な安定と強度を優先した現在の案が採用され、現行まで使用され続けていたのである。
しかし長弓兵の登場――それによる魔術的「土台」となる長弓そのものの根本的改良が進む事によって、これら魔術を取り巻く状況もまた変わる。
過去の弓に施されていた魔術類のうち、施術可能な表面積(*1)の半分以上を占めていた二点――飛距離強化の問題が物理的技術面の向上で解決し、筋力の分野については新たな装備に主要的に割り振られる事で解決をみた。
また、弓丈が伸びた事で、必然的に配置出来る面積自体も増えることとなった。
言い換えれば「魔術が干渉し合わない程度に配置できるだけの場所が空いた」のだ。
この事態を踏まえ、術の魔術構造そのものを見直す事で、装備のさらなる強化が出来るのではないか、という意見が開発チーム参加メンバーの間から出始めるようになった(*2)。
当初は長弓の改良途中ということもあり、また、魔術による必要以上の増強という点から難色を示していたるしにゃん上層部だったが、最終的に長弓の再開発が成功で終了した事から、それとは別方向の、しかし弓兵部隊の更なる改良を目指すものとして、この計画にゴーサインが出されたのだった。
……ただし、この時提出された公式文書内において、これらの計画はあくまでも「効率的な魔術構造の構築と、弓兵の可能性を模索する」試みであったことを、ここに明記しておく。
2.方向性の錯綜
「そもそも、イグドラシルからの未来情報に因れば、我々が作ろうとしている先にあるものは『弓』でした」
「……?」
「つまり現状のように『弓矢を使う』ことに拘る必要性はない。そういうことです」
〜上層部への第三次報告会議、議事録より抜粋
上層部の鈍重ともいえる動きとは裏腹に、実際の開発チームの動きは実に提言の提出直後から開始されていた。
この時期の開発の方向性は提言で示した通り「魔術構成の再構築と配置の最適化による弓の威力強化」であり、それ自体は非常に順調に行われた。
しかし、最初の射出実験で判明した思いも掛けない事実から、これら「真っ当な」方向性からの強化計画は早々に頓挫する。
問題となったのは弓ではなく、矢の方だった。
強化された速度によって発生した摩擦熱に矢が耐えられず、発火、目標地点――理論値上の数値であり、戦闘機の飛行高度である一万メートルよりもはるかに手前、高度にしておよそ1000メートルほどで焼失してしまったのである。
以後、三度に渡って様々なアイディアによる矢の強化と、それを使用しての実験が行われた(*3)が結論としては、いずれもが失敗に終わった。
この事が、チームに発想の転換を迫る事となる。即ち「攻撃手段としての矢を打ち出すスタイルの放棄」である。
実験と試行錯誤の末に、彼等はこう考えたのだ。
―――実弾兵器としての「燃え尽きない矢」を作る事は不可能である。
ならば、これを燃え尽きないもの――すなわち実体のない魔術そのものを打ち出す兵装として特化させればよい。更に突き詰めていくならば、打ち出すものが「魔術」で在る以上は、発射させる為の機関が弓として成立している必要性すらない。それどころか、それを実際に戦場で使用する人間が弓兵である意味もない。
むしろこれらの実験結果を基礎データとして捉え、新たに魔法使いたちの詠唱戦闘能力を強化する為の装備として、再度の作成を行う方がはるかに得策である―――
なんとも合理的な――しかし当然とも呼べるこの大胆な方向転換は、しかし、上層部に打診される直前で破棄されることとなる。
それに異議を唱えた者たちがいたのだ。
開発スタッフの中でも使用試験チーム、特にそれまでの膨大な試射実験に対し、惜しみない協力を行ってきた、現場の弓兵たちである。
3.静かなる戦
「星見塔の方々、あるいは政庁の皆様に申し上げる。
我等は、かの大災厄の原因たるものは、魔術にあると伝え聞いております。
なればこそ魔術だけが、かの不思議の力だけが、国を守る『力』であることの危険性は、皆様方が一番良く知っていることではないでしょうか。
幾度の危機を経て、今やこの国に魔術の徒を憎む者は減りました。しかし、あの大災厄の日々より後、国の民にその力の凄まじさを恐れる者が多い事もまた事実なのです。
であればこそ我等は思うのです――魔術以外の力で国の為に尽くす事が出来まいかと。
或いは、それらが等しく扱われればこそ、国も平穏となりはすまいかと」
〜弓兵部隊代表者による嘆願書・抄訳より一部抜粋 (原本は忍文字による為、抜粋不可)
アイドレス、否、ニューワールドの歴史において、弓兵は長らく「奇兵」であった。
この場合、奇兵とは文字通りの「異質な兵」を意味する。
こうした考えが一般的である理由にはI=Dの存在が大きい。かの機兵――歩兵より遙かに速度と戦力に優れる存在が戦力の主流である以上、それを運用した方がはるかに楽であり、またそうした兵士たちは、レムーリア等の局地的な低物理域戦闘においてのみ必要とされる存在と考えられてきたからである。
唯一、そう呼ぶに足るだけの戦力を保持するここ、るしにゃん王国においても、その状況はさほど変化するものではない。建国の頃より、長らく理力とその応用たる詠唱魔術による戦闘を重視してきたこの国においても、弓兵は長らく異質な存在であった。
過去の戦役において果たした具体的な「成果」が世間で認識されていない事もまた、この事態に拍車をかけたといえるだろう(*4)。
あるいは、こうも言えよう。
彼等弓兵たちにとっては、それまでの開発計画は日陰者であった彼等に光が当たったに等しかったのである――それが勝手に折られ、かつその成果が目の前で費えようとしており、成果は全て他者のものとなるという。
反発は必至であり、当然でもあった。しかし、同時にこれまでひとつの目的の為にと、力を尽くしてきたという情も彼等にはある。他意がないことも知っていた。
故に上層部への嘆願書を下書きの段階で敢えて流出させ、開発チーム幹部に届けさせた。
横から冷や水を浴びせた、ともいえる。諸所の事情から弓に特化させたとはいえ、元は忍者である。こうした情報戦はお手の物であった。
―――我々は怒っている。しかし、これを表沙汰にして掻き乱すつもりはない。
慌てたのは結論を示した開発チーム上層部であった。そこまでの逆鱗に触れるとは、思ってみなかったのである。とはいえ、方向性が錯綜しているのも事実である。では、どうするのか。
……ここでようやく彼等は、扱う者たちに目を向ける。
即ち、弓兵が用いることで最大限に威力を発揮する魔術兵装の開発に取りかかったのである。
4.「魔法弓手」
「うーんうーんうーん」
「悩んでますね」
「だって無茶言うんだもん。既存品の改良で魔法の矢とか無理。でも愛用の弓とか持ち変えるの嫌って話でー……あああああ」
「いっそ魔法の矢が撃てる弓を魔法で作ってしまえばいいのでは?」
「……それを早く言ってー!」
〜とある日の会議休憩中の会話。担当者、かなりぐるぐるしていたらしい。
弓兵たちの意見を元にして新たな方向性を模索する際、もっとも重要とされたのは既存の能力を殺さないようにする事、である。
これは弓兵たちの強い要望であると同時に、過去にいくつか報告されている「魔術の通用しない相手」に対処する際のリスクを踏まえた結果として出された結論であった。
この為、それまでの形であった弓そのものを新たな専用装備として作り上げるという方法は廃し、従来の装備に準じる形で装備を新設。そこに魔法射出の為の術式を組み込み、通常の弓矢と使い分ける、としたのである。
いくつかの試案の末、採用されたのは小手に魔術を組み込む案である。これにはいくつか理由があるが、実際の射出の感覚に近いものが再現されることを重視した結果による。
作成には、魔術兵器としてNWで広く知られる未婚号が参考にされており、その流麗なフォルムや塗装、魔術様式等から影響を伺う事が出来る。
小手に組み込まれた術式については秘儀として詳細は明らかにされていないが、基本的に収束した魔力を使用して「魔法による弓」を展開、魔力を矢として打ち出すものである。また、魔力を使用するという経験に乏しい使用者の魔力収束・制御を補助する役割も担う。
また照準やタイミングといったものは、弓兵としてのそれに準じるという形で落ち着いた。これもまた「魔法に頼り過ぎない」という意志の現れであるといえる。
「万能の道具に頼り切るのではなく、人の努力の積み重ねによる力を」
その発露として――彼らは自らを魔法弓部隊ではなく、魔法弓手部隊、と称する。
魔法弓を引く手であると。
最後に、魔法弓手たちの中のジンクスを紹介して筆を置きたい。
彼等の中では矢を打ち出す際、必ず片目を瞑る事が暗黙の了解として知られている。
比較的新しい職業である筈の魔法弓手たちの中で、この不可思議な行為がいったいいつ発生したかについては未だ判っていない。
ただ一つ判明しているのは、理由は様々ながらこのジンクスを魔法弓手の全員が何の疑問もなしに取り入れているという事実である
――そこから考えれば、これは何らかの魔術的な作用によるものなのかもしれない。
5.おまけ 更なる進化を
「うーん……」
「悩んでおられますね。例の部隊のことですか?」
「ええ。特化することで鍛えられているとはいえ体への負荷の問題もありますし、これ以上の魔術の重ね掛けや重装備化は避けたいところなんです。一体どうしたものかと……」
「そうだなあ……今、必要なのは―――」
「1.学術的見地の導入かな
2.弓の更なる強化かな
3.迎撃の実戦訓練かな。さあどれだ」
「アドベンチャーゲーム的選択肢出た!? しかもどれも方向性違いすぎる!」
「じゃあ『4.せっかくだから全部フォローするぜ』で」
「何気なく全許可されたーーーー?!」
〜ある日の定例会議。ふざけているようだが大真面目である
この為、魔法弓手たちの間では一種の研究会が立ち上げられる事となった。
その日だけは彼らも装束を脱いで絹の服装を身に纏い、森の王宮の会議室や隠れ里にその身を寄せ合っている。
これらは過去の試射データなどを踏まえ、よりよい撃ち方を追求する為に関係者たちが自主的に作ったものであり、日々活発な意見交換が成されている。
とはいえ、ネコノツメは個々人に合わせた調整が成されており、また個人の癖がある為、必ずしも結果は一定とならない。ここから最終的なところは個々の訓練で調整、会得するものである――との暗黙の了解がもたれていることは言うまでもない。
また、彼らの中で今、特に熱心に行われているのは空の敵に対する迎撃訓練である。
遠距離からの攻撃を得意とする彼らにとって、空からの脅威はもっとも恐れるべきものであるからだ。高度、精度、数ともに成果は徐々に上がっており、将来的には本格的に飛行機を狙えるようにする――という話もある。
努力しているのは魔法弓手だけではない。
魔法使いたちに言わせれば「ネコノツメ」は未完成品だという。
命中精度の向上や、機能の追加といった基本性能の充実の他に専用鏃の開発等、改良の余地は多い。他の装備品との兼ね合いから、盛り込まなかった機能も少なくないという。
素材の重量や強度といった分野もその中には含まれている。
いずれは要塞を一撃必殺、が彼らの中での合い言葉である。